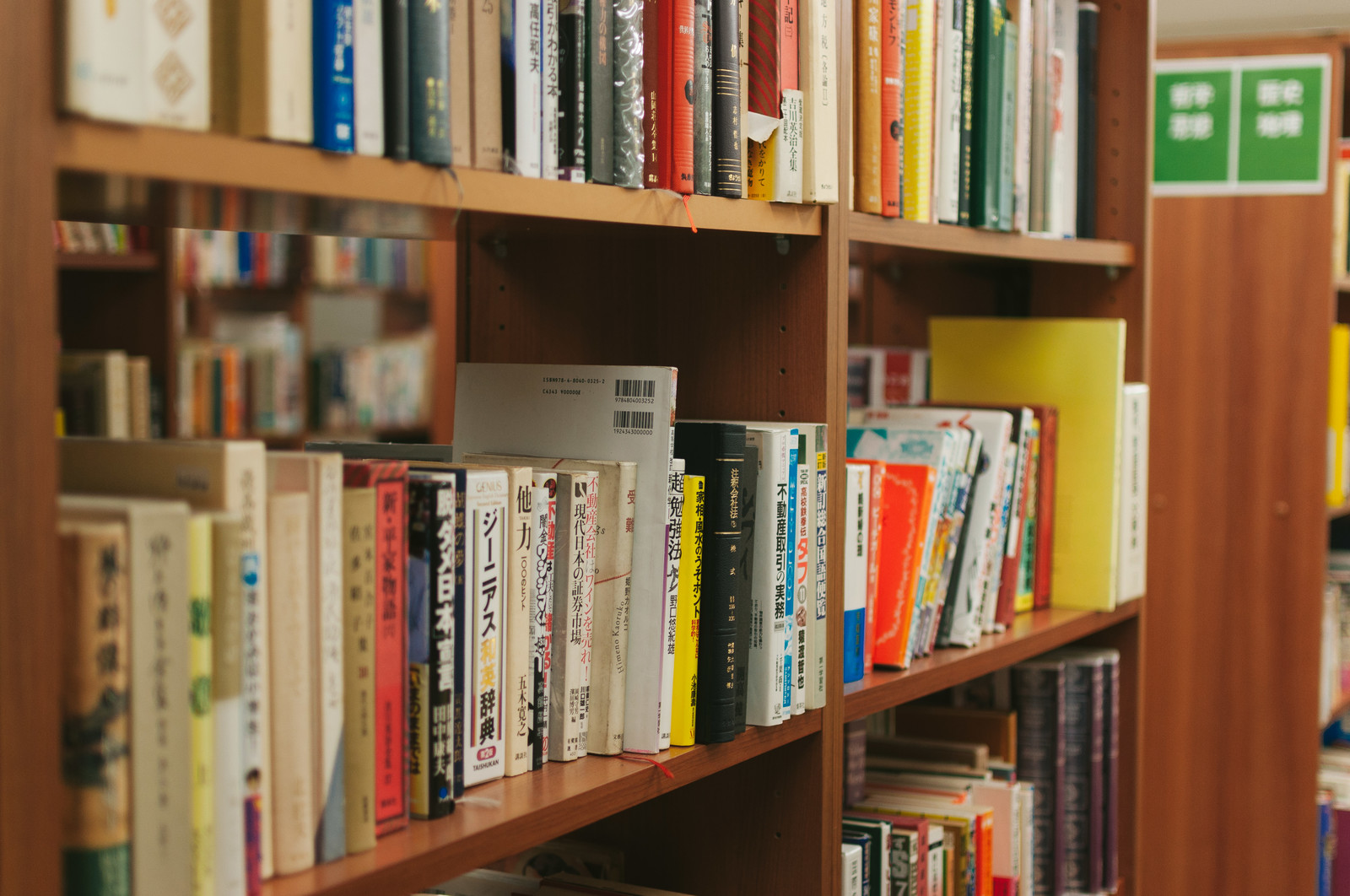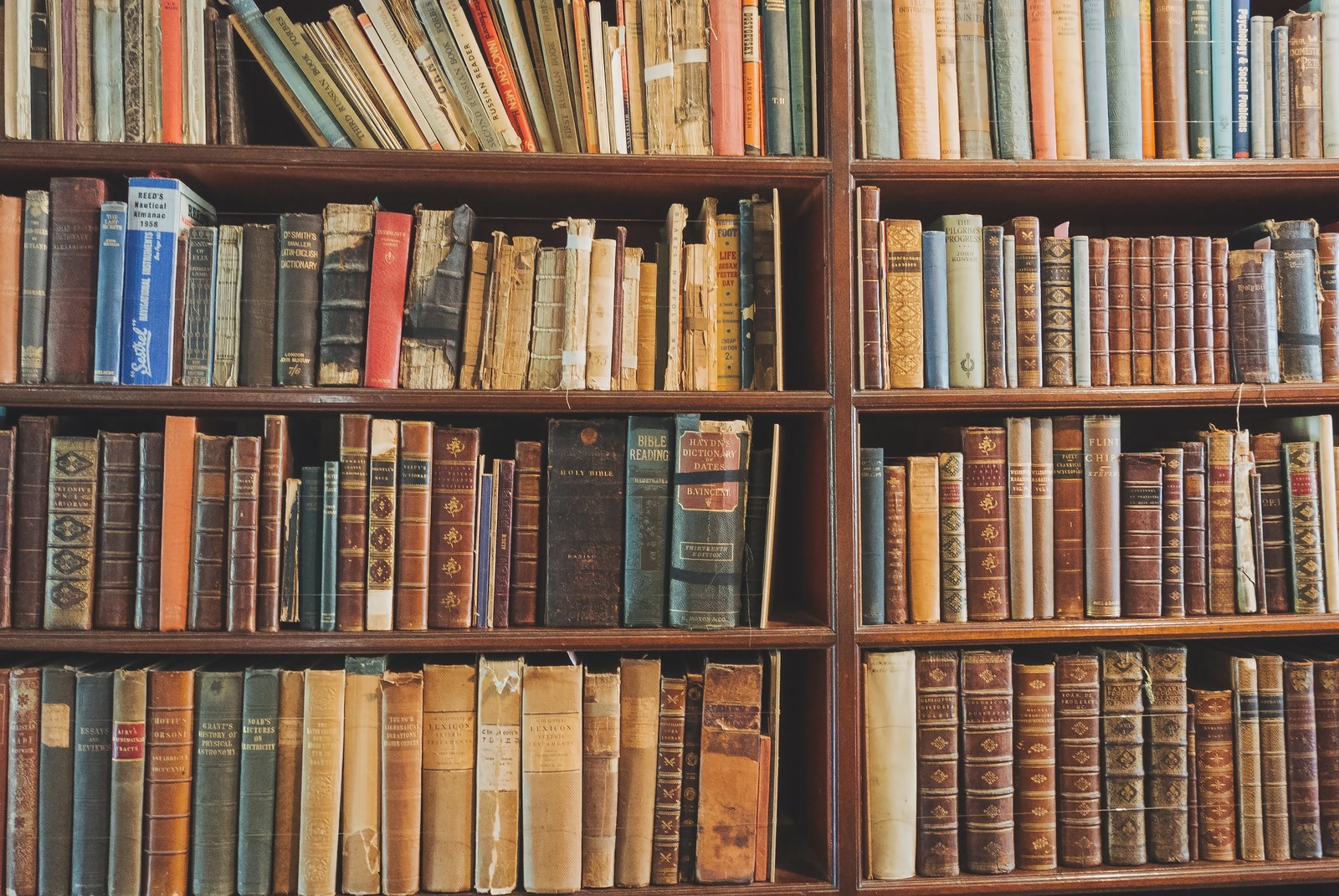《読書感想・要約》断糖のすすめ 糖質を減らせば体重も減る!

2021『断糖のすすめ ~高血圧、糖尿病が99%治る新・食習慣~』
以前から「糖質制限」が流行っておりますが、この本は「断糖」です!ゆる~くやっていこうと思っていた私にはお手厳しい言葉(笑)
しかし糖がいろいろな病気にも関係していることを、教えてくれる本になります。
Contents
本・著者の紹介

断糖のすすめ ~高血圧、糖尿病が99%治る新・食習慣~
【著者】西脇俊二
数々の人気ドラマの医療監修を担当した名医。精神科医としての実績だけではなく、「断糖」「消化力を高める」など独自の理論で、現代人の病気や不調の完治・改善に努めてきた。現在は、ハタイクリニックの院長として診療をしながら、メディア出演、医療監修、執筆など多数の分野で活躍中。
講演依頼.comさまより引用
【目次】
第1章 現代人にとって、糖は「毒」である
第2章 たいていの病気は「断糖」で完治・改善する
第3章 3日間で実感! 断糖ダイエット
第4章 ボケない断糖の法則
第5章 人生を変える「断糖マニュアル」
Amazonの紹介ページを見ると、目次の他に【「断糖」で完治・改善するもの】が書かれていて◎高血圧 ◎糖尿病 ◎動脈硬化 ◎統合失調症 ◎パニック障害 ◎肥満 ◎がん ◎うつ ◎老化 ◎不眠症 ◎痛風 ◎手足の冷え など
となっております。糖尿病や高血圧は想像できましたが、がんやうつまでも!?さらには老化の防止効果もあるとは!食べるものを変えるだけで、簡単に健康が手に入りそうです。
要約・気付き
断糖とは
この本ではタイトル通り「断糖」をお勧めしてます。
数年前から「糖質制限」が流行っていますが、「断糖」なので摂取量を減らそうというものではなく、完全に糖を断とうという内容です。ゆる~く制限しようとしていた私には拷問のような題名です(笑)
普段から私達が口にしている、ほとんどの食べ物には糖が含まれています。スイーツはもちろんのこと、パンやお米などの炭水化物から、果物や野菜さらには調味料まで!これまで無意識に糖を摂取してしたと分かり、少し怖くなります。
それでは逆に食べられるものは?というと、肉や魚、豆腐といったタンパク質を中心に、根菜など甘いもの以外の野菜、海藻、キノコ類になります。
読み進めると厳しい内容に、自分は本当に実践できるのか不安になってきます。投げ出したくなる気持ちを抑え、まずは考え方を教えてもらおうと頑張って読みました(笑)
野菜の糖質
糖質は、私たちが日常的に食べているご飯やパン、麺類・果物・野菜などにも含まれます、これこそがクセ者なのです。
本書より引用
「糖」で思いつくのは単純に砂糖の多く入った、ジュースやスイーツ、甘いお菓子でした。さらに最近では炭水化物が糖になると、お茶のCMでも教えてくれてます。
しかしこの本を読むと、果物だけではなく、種類によっては、野菜にも多く含まれているという事がわかります。実際に糖の多い野菜を調べると、この表のようにかぼちゃやとうろもこし、そして根菜にも多く含まれていることが分かります。
| 食品名 | 量 | 糖質量(g) | 100g当たりの糖質量(g) |
| かぼちゃ | 120g(1/8個) | 20.50 | 17.08 |
| とうもろこし | 150g(1本) | 20.70 | 13.80 |
| れんこん | 120g(1節) | 16.20 | 13.50 |
| そらまめ(ゆで) | 40g(10粒) | 5.20 | 13.00 |
| ごぼう | 50g(1/4本) | 4.90 | 9.80 |
| 玉ねぎ | 180g(中1個) | 13.00 | 7.22 |
| 人参 | 130g(1本) | 8.50 | 6.54 |
| ミニトマト | 15g(1個) | 0.90 | 6.00 |
| トマト | 200g(1個) | 7.40 | 3.70 |
| キャベツ | 45g(葉1枚) | 1.50 | 3.33 |
玉ねぎは血液をサラサラにしてくれる効果があると聞き、味も食感も大好きだったのですが、この表を見て驚きました。食べすぎには注意です!

その他の食品の糖質
野菜にも糖質量が多く含まれていることに驚いてましたが、本書では他にも麺つゆやケチャップなどの調味料にも糖質が多く含まれている事を教えてくれます。
インターネットで調べるとこの表の通り、普段気にせずに食べていた調味料が思ったよりも高い数値だった事が分かります。
上白糖 小さじ1・・・・・・・3.0g
本みりん 小さじ1・・・・・・2.6g
トマトケチャップ 大さじ1・・・3.8g
ウスターソース 大さじ1・・・4.7g
中濃ソース 大さじ1・・・・・5.3g
焼き肉のたれ(中辛)大さじ1・・・5.5g
カレールー 20g・・・・・・・8.2g
はちみつ 17g・・・・・・・13.5g
西京みそ(白みそ)10g・・・3.2g
固形コンソメ 4g・・・・・・1.7g
オイスターソース 小さじ1・・・1.1g
めんつゆ(3倍濃縮)小さじ1・・・1.2g
料理酒 大さじ1・・・・・・・2.7g
小麦粉(薄力粉)大さじ1・・・6.5g
片栗粉 小さじ1・・・・・・・2.4gFURDIさまより引用
この表を見てガックリきました。毎朝、自分で作ったハニーナッツではちみつを食べてますし、カレーも大好き!なのに両方とも高い数値だったのです(笑)
さら読み進めて驚いたのが「ブラックコーヒー」にも糖質は含まれているのです!調べてみると100g中に0.7gの糖質があるそうです。低い数字なので私は気にせず毎日の様に飲んでますが、植物からできているモノには微量でも含有されるそうです。
「断糖」となるとこれらの食べ物なども、口にすることは避けなければなりません。辛いですね(笑)
これまで我が家は「糖質無制限」だったので(笑)、大好きなパンを朝昼晩と連続して食べることも普通にありました。
しかし「糖質制限」を始めてから、普通のパンは禁止にしました。お米も「もち麦」を入れて食物繊維を増やし、炊く時に入れるだけで糖質カットするアイテムを使うようにしました。平日お昼に食べていたお弁当も、LAWSONのブランパン(低糖質)に変えました。
毎日体重計に乗ることも必要です。制限を始めると、体重がドンドン減るのが楽しくなります。始めた頃の体重は66kgでしたが、1ヶ月の間に食べ物を制限するだけで62kgまで減りました。
あまり減りすぎるのも不健康そうに見えて(笑)良くないと思い、その後は緩めの制限に変えました。
糖と脳内ホルモンの関係
「本書の紹介」でも気になった「うつ」に効果があるのは、どういうこと?と読み進めました。
結論としては「脳内ホルモンに影響があるから」ということになります。
人間の脳内では普段、脳内ホルモンと呼ばれるドーパミンやノルアドレナリン、セロトニンなどが、バランスよく分泌され精神的に安定してます。
糖を摂取すると血糖値が上がります。血糖値が上がると体を傷つけてしまうので、それを防ぐために膵臓からインスリンが分泌され、血糖値の上昇を抑えます。
この時の必要以上に分泌されるインスリンが、自律神経を刺激し、さらにそれが脳内ホルモンの分泌に異常をもたらし、ドーパミンなどの分泌量が減ります。自律神経が刺激されドーパミンの分泌量が減ることで、うつをはじめとする健康障害が引き起こされるのです。つまり、うつ病の原因は「糖分の摂り過ぎ」かもしれない、ということです。
さらにインスリンは血糖値を下げる過程で、血中の糖分を脂肪に変えてからだに貯め込むように働きます。これが太る原因になります。
食べ方にも注意
空腹状態にいきなり大量の糖質を摂取してしまうと、血糖値が一気に上昇してインスリンが大量に分泌されてしまいます。
これを避けるためには、「食物繊維」が多く含まれる野菜やキノコ、海藻類から先に食べることが大切です。食物繊維は糖の吸収を穏やかにしてくれます。
そしてゆっくり良く噛んで食べることで、さらに糖の吸収スピードを抑えてくれるので、血糖値も上がりにくくなります。
どんなにお腹が空いてても、サラダから良く噛んでゆっくり食べ始めましょう!

GI値からGL値
本書を読んでから糖質制限を開始しようと思いましたが、食べれるものが野菜とお肉だけになって、普段の食生活からかけ離れすぎてしまい現実味がありませんでした。
しかしせっかく本を読んで知ったのに、何もしないのは勿体ないと思い「GI値」から調べてみました。
GI値とは
糖質制限を調べてみると「GI値」という言葉を良く目にします。テレビなどでも良く聞いていた言葉でしたが、理解をしていなかったでの調べてみました。
GI値(グリセミック指数、Glycemic Index)
食事で糖質を摂取すると血中に入って血糖値が上昇します。すると膵臓からインスリンというホルモンが分泌され、糖分を細胞に取り込みますが、余るとインスリンはそれを中性脂肪として脂肪細胞に蓄えさせます。
そこで、インスリンがあまり分泌されない(=低インスリン)食品を食べればダイエットできる、というのが低インスリンダイエットの考え方です。そのとき、各食品の血糖値の上昇度合いを示す指標として利用されたのが、GI値でした。
ミモレさまより引用
それまで食事をする時に、カロリーだけを気にしてましたが、それよりも血糖値を上昇させることが太る原因なんだと理解できます。
このGI値はどういう計算で算出されているのか?というと何か食品を食べたときに、血糖値が上がるスピードを計測した値です。
その食品に含まれる糖質量が50gになるまでに食べた時、ブドウ糖50gの上昇スピードを100としたらどのくらいになるかというものです。
ん?ここで気になるのが、糖質量が50gになるまで食べた時ということは、人参で言うと5~6本食べた時の、血糖値の上昇速度の事になります。って馬か!(笑)これまで一度の食事でその量の人参を食べたこと無い!
ということで、GI値はある程度の目安にはなるけど、この数字だけでは何を食べて良いのか悪いのか良くわからないです。
GL値とは
そこで考えられたのがこのGL値です。海外では既にGI値からGL値が当たり前になっているようです。
GL値(グリセミック負荷、Glycemic Load)
食品100g中に含まれる糖質量(g) × GI値 ÷ 100 この計算方法で算出されます。これで食材を100g食べた時(約一食分)に、どの食材が血糖値を上げるリスクがあるか分かります。
GL値はGI値に比べ小さい数字になります。ちなみに10未満は低GL値、11~19は中GL値、20以上は高GL値に分けられます。
比較表
分かりやすくGI値とGL値を並べてみました。
果物 GI値 GL値 スイカ 72 4 レーズン 64 28 バナナ 62 16 マンゴー 51 8 リンゴ 40 6 プルーン 29 10 比較的GI値が高い果物でもGL値に置き換えてみるとこれだけの数字の違いに。高GI食品だからと単純に敬遠していた食品も、これからはその食品が含む炭水化物の割合を考えて食べる時代だ。 Tarzan さまより引用
スイカを例にとってみるとGI値が72と高いけど、計算してGL値を出してみると4になり低GL値の食品になります。他の果物もGI値を気にして食べないようにしてましたが、食べすぎない程度にすれば問題ないレベルです。
他の食材のGL値も調べてみると、やはりパンやご飯等の炭水化物が「高GI値」であり「高GL値」になってます。
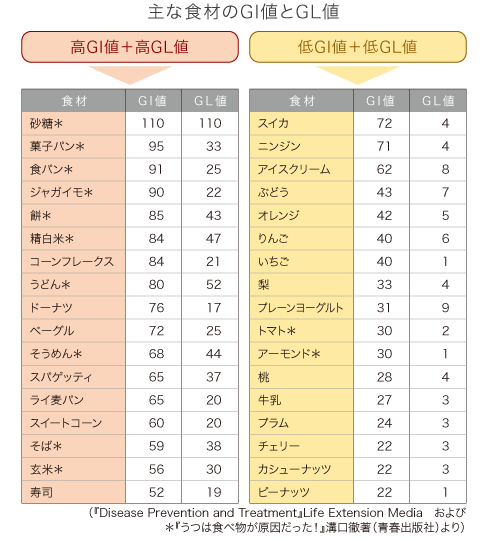
GL値が20以上の食材は量を減らしたり、なるべく食べないように避けて、GL値10未満の食材は好んで食べれば健康になるということが分かります。
我が家では毎朝飲んでいる「牛乳」も、糖質量やGI値を調べると高い数値だったので、朝の牛乳はお茶か水に変えようとしましたが、GL値を見ると3なので低GL値食品だったということが分かり安心して飲み続けようと思います。
各食品のGI値ではなく「GL値」を調べることが大切でした。
まとめ
この本を読んでから妻とも話し合い、我が家では断糖ではなく「糖質制限」を開始しました。
糖質制限の食材や商品を探してみると、大好きなパンやケーキなどの食べ物は種類も多く販売されていて美味しいモノが多いです!さらに糖質カットしてくれるアイテムや電化製品もあって、探すもの楽しいです。
炊飯器に入れるだけで糖質カットができるアイテムです。
糖質を最大20%カットできる炊飯器です。
ただ食べたいものを買うのではなく、GL値や糖質量を調べながらの買い物は、新しい扉を開いた感覚で(笑)楽しくて、より健康になれると思うと夫婦で協力もできます。
この本をキッカケに糖質制限を調べて始めることができて、このブログ記事を書くためにGI値やGL値のことを調べてとても勉強になりました。
私は本を読んでアウトプットすることで、自己成長したいと思っているので、実践ができて自己肯定感が上がり、ドーパミンが分泌されてさらに健康になれそうです(笑)
これからもいろいろな分野の本を、読んで勉強していきたいと思います。